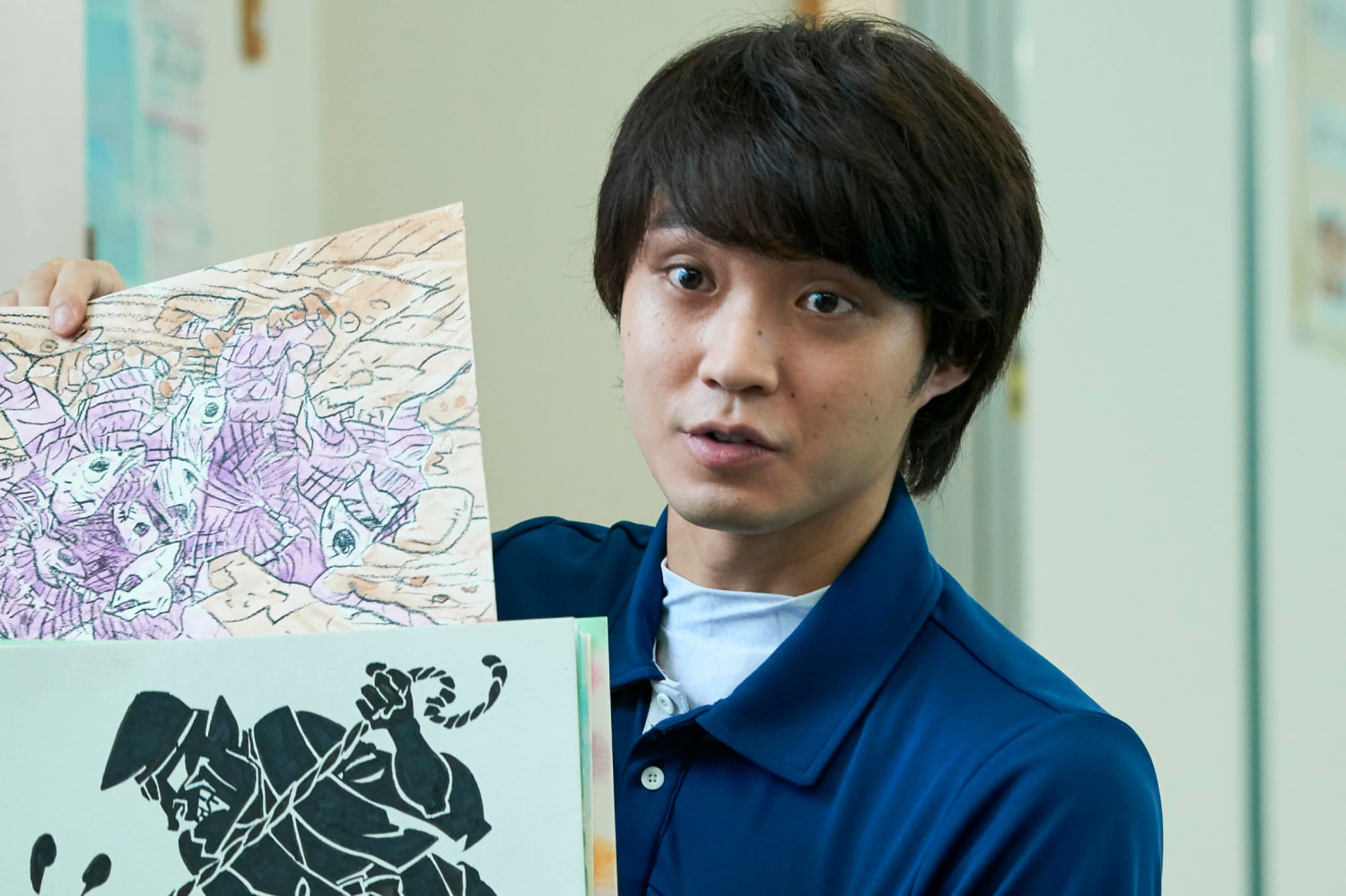Trailer
特報
Introduction
解説
実際の障害者殺傷事件を題材に、2017年に発表された辺見庸の小説「月」。
本作は、『新聞記者』、『空白』を手掛けてきたスターサンズの故・河村光庸プロデューサーが最も挑戦したかった原作だった。
それを映画化するということは、この社会において、禁忌とされる領域の奥深くへと大胆に踏み込むことだった・・・。
オファーを受けた石井監督は、「撮らなければならない映画だと覚悟を決めた」という。その信念のもと、原作を独自に再構成し、渾身の力と生々しい血肉の通った破格の表現としてスクリーンに叩きつける。
そして宮沢りえ、オダギリジョー、磯村勇斗、二階堂ふみといった第一級の俳優陣たちもまた、ただならぬ覚悟で参加した。本作は日本を代表する精鋭映画人たちによる、最も尖鋭的な総力をあげた戦いだといっても過言ではない。
もはや社会派だとか、ヒューマンドラマだとか、有り体の言葉では片づけられない。
なぜならこの作品が描いている本質は、社会が、そして個人が問題に対して“見て見ぬふり”をしてきた現実をつまびらかにしているからだ。本作が世に放たれるーそれはすなわち、「映画」という刃が自分たちに向くということだ。覚悟しなければならない。そう、もう逃げられないことはわかっているからー。




Story
物語
深い森の奥にある重度障害者施設。ここで新しく働くことになった堂島洋子(宮沢りえ)は“書けなくなった”元・有名作家だ。彼女を「師匠」と呼ぶ夫の昌平(オダギリジョー)と、ふたりで慎ましい暮らしを営んでいる。洋子は他の職員による入所者への心ない扱いや暴力を目の当たりにするが、それを訴えても聞き入れてはもらえない。そんな世の理不尽に誰よりも憤っているのは、さとくんだった。彼の中で増幅する正義感や使命感が、やがて怒りを伴う形で徐々に頭をもたげていく――。
Staff
スタッフ
石井裕也 監督・脚本
1983年6月21日、埼玉県出身。
大阪芸術大学の卒業制作として監督した作品『剥き出しにっぽん』(’05)が、第29回ぴあフィルムフェスティバルでグランプリを受賞。
第37回日本アカデミー賞で『舟を編む』(’13)が最優秀作品賞、最優秀監督賞を受賞。
他の監督作に、『ぼくたちの家族』(‘14)、『バンクーバーの朝日』(‘14)、『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(’17)、『町田くんの世界』(’19)、『生きちゃった』(’20)、『茜色に焼かれる』(’21)、『アジアの天使』(’21)、『愛にイナズマ』(’23)などがある。
河村光庸 企画・エグゼクティブプロデューサー
1949年8月12日生まれ、福井県出身。
08年にスターサンズを設立。12年、製作・配給をした『かぞくのくに』(ヤン ヨンヒ監督)で同年の映画賞を席巻。17年には『あゝ、荒野』(岸善幸監督)が日本アカデミー賞(最優秀主演男優賞)受賞のほか、各賞の話題を集め、その後も『宮本から君へ』(19/真利子哲也監督)、『ヤクザと家族 The Family』(21/藤井道人監督)、『空白』(21/吉田恵輔監督)、『ヴィレッジ』(23/藤井道人監督)などをプロデュース。映画『新聞記者』(19/藤井道人監督)では日本アカデミー賞で作品賞を筆頭に6部門で優秀賞を獲得した。
本作の撮影直前となる2022年6月11日、逝去。
鎌苅洋一 撮影
1979年生まれ。
『俳優 亀岡拓次』(’16 横浜聡子監督)で商業映画デビュー。『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(’17)『茜色に焼かれる』(’21 共に石井裕也監督)、『花束みたいな恋をした』(’21 土井裕泰監督)、『1秒先の彼』(’23 山下敦弘監督)、などで撮影を担当する。
公開待機作として『笑いのカイブツ』(’24 滝本憲吾監督)が控えている。
長田達也 照明
1952年山梨県出身。
1983年より映画の照明技師としてデビュー。『Shall we ダンス?』(96)で日本アカデミー賞最優秀照明賞を受賞。石井裕也監督作品『舟を編む』他8作品で日本アカデミー賞優秀照明賞を受賞。主な作品『シコふんじゃった。』(92)『ウォーターボーイズ』(01)『陰陽師』(01)『壬生義士伝』(03)『それでもボクはやってない』(07)『ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~』(09)『空飛ぶタイヤ』(18)『カツベン!』(19)『茜色に焼かれる』(21)他多数の作品に参加。
2020年芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。
髙須賀健吾 録音
『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(17/石井裕也監督)で毎日映画コンクール録音賞を受賞。
これまでに『ミックス。』(17/石川淳一監督)、『あいあい傘』(18/宅間孝行監督)、『春待つ僕ら』(18/平川雄一朗監督)、『映画 コンフィデンスマンJP 全シリーズ』(19~22/田中亮監督)、『滝沢歌舞伎 ZERO The Movie』(20/滝沢秀明監督)、『胸が鳴るのは君のせい』(21/高橋洋人監督)などがある。
岩代太郎 音楽
東京芸術大学大学院修了。
国内外を問わず数多くの映像作品の音楽を担当。映画「血と骨」「春の雪」「蝉しぐれ」「利休にたずねよ」「Fukushima 50」「キネマの神様」で日本アカデミー賞優秀音楽賞、「闇の子供たち」で毎日映画コンクール音楽賞を受賞。またジョン・ウー監督『レッドクリフ』『The Crossing』『Manhunt』、ボン・ジュノ監督『殺人の追憶』も手掛ける。TVでもNHK連続テレビ小説「あぐり」、大河ドラマ「葵・徳川三代」「義経」なども担当。
2018年より、演劇と音楽のあたらしいカタチの舞台「奏劇」を企画し、自らの原案・作曲・演奏で公演を行っている。
Comments
コメント
著名人からのコメント *敬称略/50音順
雨宮処凛(作家)
『相模原事件裁判傍聴記 「役に立ちたい」と障害者ヘイトのあいだ』著者
「彼」はおそらく嗅ぎつけていたのだ、私たちの中にある「内なる優生思想」を。観る者すべてが試され、揺さぶられ、問われる覚悟の一本。
岩井志麻子(作家)
きれいごとの何が悪い。事実の追求や真実の究明より、きれいごとをいかに事実や真実に近づけられるか、そこに懸命になることが生きることであり、そのきれいごとを信じられるのが人間である。
恩田泰子(読売新聞編集委員)
石井裕也監督の「月」は、広く公開され、たくさんの人に届けられなければならない。
この映画は、苛烈にして誠実な表現をもって、人や社会をぬくぬくとくるんできたきれいごとを剥がし、見ているふりをして見ていなかったこと、考えているふりをして考えていなかったことを突きつけてくる。もう逃げたり、ひるんだりしているわけにはいかない。
カオスの中でつつましくまたたく希望のかけらを見つけ出すために。この映画から、しっぽを巻いて逃げ出したら、それこそもう絶望しか残らないのだ。
見城徹(編集者)
この社会に蔓延る[嘘と現実]、[善と悪]、[建前と本音]の判断を宙吊りにしたとてつもない映画だった。「月」は誰もが当たり前のように見ているが、実は誰も本当に存在しているのか解らない曖昧なものでもある。しかも、「月」は太陽の光に照らされて様々に姿を変える。だから、「月」はロマンチックな影を人間の心に落とすのだ。オダギリジョーと宮沢りえ夫婦が直面する[圧倒的な現実]と磯村勇斗の心に影だけを落とす[月]はライバルのように激しくせめぎ合う。後半は磯村勇斗の狂気(=ルナティック=月)を誰も否定出来なくなるが、ラストに宮沢りえがオダギリジョーにかける一言がこの映画を万感の想いで支えている。
身動きも出来ないまま観終わって、まだ映画に犯されている。世に問うべき大問題作にして大傑作の誕生。石井裕也監督、此処にあり。凄過ぎる。
佐藤幹夫(ジャーナリスト・作家)
以前、「辺野古·フクシマ·やまゆり園」というタイトルの原稿を書いたことがある。いずれも戦後の長きに渡って、私たちの社会は、ここにある過酷な現実を「なかったこと」にしてきた。豊かで快適な暮らしを送るためである。
ところがある時期から、その現実が「目をそらすな」と叛乱を起こし始めた。津久井やまゆり園事件という、重度障害者施設やそこで暮らす人々の問題もそうである。私などのようにこの業界で50年も生きてきた者にとっては、今ごろになって「重度障害者が…」などと騒がれると、皮肉の一つも吐きたくなるのだが、ともあれ、まずは本作を観ていただきたいと思う。
賛否はいろいろとあるだろう。自分の中のどろどろしたものが引き出され、顔をそむけたくなり、つい席を蹴って立ち去りたくなるかもしれない。それでも最後までここに描かれた現実と(つまりは皆さん自身と)、向き合っていただきたいと思う。
私がぜひとも注目してほしいと感じたところ。俳優さんたちの「虚実」のあわいで揺れ動く、むしろ苦悶さえ感じさせる表情(これまで、「キレイゴト」をめぐる不安や怖れがこのように演出された例を、私は知らない。この映画は「表情」の劇ではないかとも思えた)。そして時に映し出される、重篤の障害をもつ当事者の人たち。彼らは自身の「存在そのもの」を訴えるような、まっすぐなまなざしをこちらに向けていた。私は、よくこんな絵が撮れたものだと、しばし感嘆した(エンドロールでは、彼ら全員の絵をつないで映し出してほしかった。じつは彼らこそがこの映画の「
そしてもう一つ、監督は文字通り死に物狂いになって、ひとかけらでもいいから、どこかに「希望」はないのかと苦闘しているように思えた。本作には、原作にはないいくつかの仕掛けが施されているのだが、二つだけ挙げるならば、一つは冒頭のシーンが示すように東日本大震災とまっすぐにつながっていることである。もう一つが、カップルを含む「三様の家族劇」としたことである。そこに重要なヒントがあるのではないか。私はひそかにそうにらんでいるのだが、ともあれ「希望の有無」をめぐる答えは、劇場を出た後の皆さんにゆだねられることになる。「月」が照らすのは、じつは皆さんや私の姿でもある。
シトウレイ
(ストリートスタイルフォトグラファー/ジャーナリスト)
意思疎通が図れない人間は生きる権利があるのか否か。
その答えを観る人に投げかける。
理性や善意、倫理や好意。
自分自身の価値基準が(図らずも)炙り出されてしまう作品。
ダイノジ・大谷(芸人)
なんと切実な映画なのだ。
人間の猛々しい剥き出しの慟哭が刻まれたような映画だ。
いつもそうだ。
月はいつも僕たち人間の隠しておきたいことや伏せておきたいことを照らしてきやがる。
本当は観たくなかった映画なのかもしれない。
そうか、この映画『月』こそが月そのものなんだろう。
僕に突きつけてくる。我々が加害者でないと言い切れるのか、と。
後ろめたい自分を炙り出す。
きっとどうしようもなく悲しいけどどうしようもなく優しいものなんだろう、人間というものは。
生きることを諦めてしまわぬように人間を諦めてしまわぬように。
観終わって今も祈り続ける。
観て本当によかったと思えた映画でした。
さぁ僕はどうしようかな。
それでも僕はやっぱり言いたいのよ、世界は素晴らしいと人間はきっと優しいものなんだと。
希望を捨てるなと月が今日も僕らを照らすよ。
高橋源一郎(作家)
『月』を観て、名状し難い感銘を受けた……と書いて、これは正確ではないと思った。ぼくが感じたものは、もっとずっとやっかいで、ことばにするのが難しいものだった。
『月』では、障害者施設を襲い、そこに収容されている人たちを殺傷した現実の事件とその犯人らしき人物がモデルとして描かれている。そこには重い問いかけがある。どんなことばもはね返してしまうような強烈な問いである。だが、その問いよりもさらに強く、訴えてくるのは「月」だと思った。映画全体をひたしている「月の光」だ。
「太陽の光」はまぶしく、すべてのものを照らし尽くす。そこではすべてが見えてしまうだろう。世界の隅々までまでくっきりと。けれども、「月の光」はちがう。ぼくたちひとりひとりを個別に照らすか細い光である。その淡い光の下でだけ、ぼくたちは「個」になるのだ。
登場人物の多くは、「ものをつくる人」である。そして、同時に「うまく作ることができない人」でもある。彼らは淡い「月の光」の下でそのことを知る。そこで生まれてくるものがある。そこでしか生まれないものが。それがなになのかぼくにはよくわからない。『月』は、あまりに強烈なテーマを扱っているので、もしかしたら観客は、そちらに視線を奪われるかもしれない。そうではない。もっとずっと繊細で、実はおぼろげなものが、そこにある。それは「生きる」ということなのかもしれない。もう一度書くが、ぼくにはその正体がはっきりとはわからない。わからないまま、ぼくはうちのめされていた。ぼくもまた、この映画が発する「月の光」の下にいたのだ。
武田砂鉄(ライター)
あの表情、つまり、「生産性がないんだから」と開き直った彼の顔に、私たちはどんな言葉をぶつけることができるのだろう。
西村博之(元2ちゃんねる管理人)
『人の命は平等』と嘯く人も、自分の手は汚さず、誰かに負担を押し付ける社会。そして、見て見ぬふりをしてるのは貴方も一緒ですよね、、と、観客まで立場を問われる映画。
フィフィ(タレント)
私達は障害者の気持ちに寄り添っているようで、見たくないものは見ないし、聞こえない声には耳を傾けない。
綺麗事ばかりで嘘つき、この世の中こそが普通じゃない…そう何度も問われて、本心が抉(えぐ)られていく。
北條誠人(ユーロスペース支配人)
私がいちばん惹かれたのはこの作品がもっている覚悟です。
決して気持ちよく観続けることのできる作品ではなく、否の声も多々でてくることと予想されます。ただ観続けていくことで、役者さん、とりわけ宮沢りえさんの表情や陰影が深い撮影、思い切りのいい編集、セリフの息づかいなどかなりの覚悟で臨まなければこれだけの作品には仕上がらなかったと思います。
石井裕也監督の今の気持ちが強烈に伝わってきました。
森直人(映画評論家)
石井裕也が命がけでぶん投げてきた灼熱の問題提起の豪球。
我々にできるのは、火傷しながらも全身で受け止めること。
『月』は告げる。もう見え透いた嘘はやめにしよう。
本気の表現しか響かない新しい時代が目の前に来ている。
キャスト/スタッフからのコメント
宮沢りえ
私が演じた洋子の心は、ずっと、今も私の中を旅しています。
この映画を観てくださった方と、その旅の先にある「何か」を掴みに行きたいです。
磯村勇斗
撮影期間中、「人」とは何か。「生きる」とは何か。ずっと考えていました。
その答えを出すことに、恐れさえ抱いていました。
でも、これは決して他人事ではなく、綺麗事を捨て、僕たちは向き合わねばならない。
今はただ、この映画を観てもらいたい。対面して欲しい。そう思っています。
二階堂ふみ
この作品について、ずっと答えを出せずにいます。
そして、答えを出すべきではないとも思ってます。
命に対して私たちは容易く傍観者になってしまう。しかしこの現実を真っ直ぐ見つめ、私たちの問題として考えたいと思い現場に参加させて頂きました。
オダギリジョー
人間は自分勝手で傲慢で、冷酷で残酷な生き物だ。
ただ、この作品が描いているのは、そんな人間の温かみであり、思い遣りであり、何ミリかの可能性である。全ての人間に突き刺さる未来への希望だ。
監督・脚本:石井裕也
この話をもらった時、震えました。怖かったですが、すぐに逃げられないと悟りました。撮らなければいけない映画だと覚悟を決めました。多くの人が目を背けようとする問題を扱っています。ですが、これは簡単に無視していい問題ではなく、他人事ではないどころか、むしろ私たちにとってとても大切な問題です。この映画を一緒に作ったのは、人の命や尊厳に真正面から向き合う覚悟を決めた最高の俳優とスタッフたちです。人の目が届かないところにある闇を描いたからこそ、誰も観たことがない類の映画になりました。異様な熱気に満ちています。宮沢りえさんがとにかく凄まじいです。
プロデューサー:長井龍
目の前の問題に蓋をするという行為が、
障害福祉に従事されている方にも本作をご覧頂き「